
多様な働き方の実現に向けて、リモートワークを導入された経営者様も多数いらっしゃることと思います。
しかし、セキュリティ面を含む各種対策をせずにリモートワークを続けるのはとても危険です。
急場しのぎでリモートワークを始めた結果、さまざまな問題が発生しているケースがあります。
問題
01
リモートワークによる生産性の低下
リモートワークで、生産性が下がったという話をよく聞きませんか?
リモートワークは社内での作業と違い、仕事の進捗を実際に見ながら管理することができません。きちんと時間どおりに仕事を始めているのか、勝手に休んだりしていないかを把握することさえ、とても困難です。
実際に、社員の中にはリモートワークを勝手に休みだと解釈して、旅行に行ってしまったケースもあります。また、リモートワーク中、社員がお手洗いに行っていただけなのに、Webカメラを通じて姿が見えないことに気がついた上司が何気なく「どこに行っていたんだ?」と聞いてしまい、そのことをセクハラに感じたりするということも起こっています。

問題
02
リモートワーク中の機密情報の漏洩
リモートワークの最大の問題の一つが、機密情報の漏洩です。
社外で業務を行うためには、社員が情報を持ち出さなければならないこともあります。しかし、誰がどの情報を持ち出したのか管理できないと、情報漏洩の抑止はできません。
実際に、リモートワークを通じて社員が機密情報を漏洩させたケースも報告されています。

問題
03
リモートワーク中の適切でない残業
残業を適切に管理する重要性は、リモートワークでも変わりません。
リモートワーク中はタイムカードで社員の出退勤を正確に管理することが難しいため、各自が自己申告した時間が残業時間になります。しかし、定時内に仕事が終わらなかった場合に、残業申請を行わず仕事を続けてしまうケースも。このように、リモートワークでは把握しづらい残業は、後に労働基準監督署の査察が入った際にPCのログイン情報から発覚することもあり、大問題です。

ほかにもリモートワーク導入のための準備不足で、さまざまな事故や事件が起こっています。
これらリモートワークの問題を、
SKYSEA Client Viewで解決します。
01リモートワーク中の
詳しい作業状況を把握
リモートワーク中は人の目が届かないため、日々の業務については従業員の申告を信じるしかありません。しかし、PCの操作状況が適切に把握できるとどうでしょうか。
SKYSEA Client Viewは、PCの操作ログを収集することで作業状況を可視化できます。

PCの操作ログを記録・管理できます
PCを使用した業務を行っている場合に、社員がリモートワーク中にどのような作業をしていたのかログから確認できます。例えば、この画面の操作ログでは、プレゼンテーション用のソフトウェアで資料ファイルを作成したり、印刷していることがわかります。

02リモートワーク中の
情報漏洩リスクを軽減
リモートワークであっても誰が特定の情報を閲覧、ダウンロードしたのかを記録。万が一、情報漏洩が起きた場合でも、ログから追跡、操作できます。

ファイルの操作状況を追跡できます
例えばこの画面では、社外秘の顧客リストをサーバーからダウンロードし、ファイル名を「スケジュール」に変更してUSBメモリへ書き込んだことがわかります。

03リモートワーク中の
作業時間・残業時間の見える化
PCの電源ON / OFFの状況や、各時間帯でのPC操作に関するログを集計し、レポート化することで、リモートワーク中の従業員の作業時間・残業時間を視覚的に確認できます。

従業員の作業時間などをダッシュボードで可視化できます
1日の業務時間におけるPCの操作率や操作時間を視覚的に確認できる機能を搭載。また、操作時間を組織で規定された定時時間と並べて表示することで、休憩時間が適切に取られているか、申請なしに残業が行われていないかを把握するのにも役立ちます。

今からでも遅くありません!
適切なリモートワークのための対策強化を。
クライアント運用管理ソフトウェアの決定版!
累計導入実績2025年05月31日現在
23,589社
12,394,817クライアント
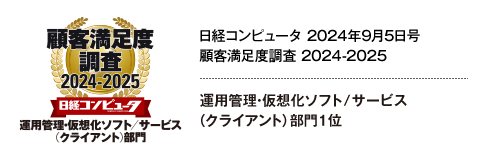
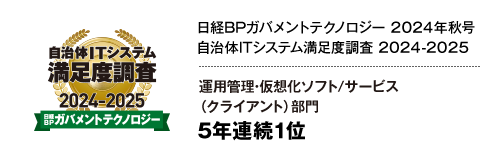
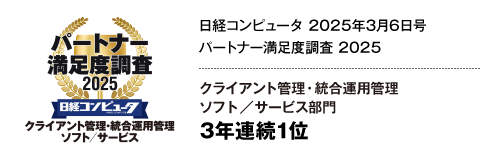
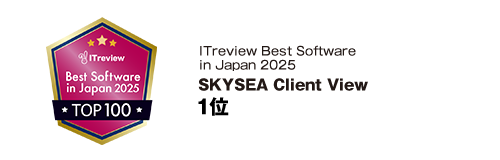
※日経コンピュータの調査は、製品ではなく企業を対象にしたものです。
富士キメラ総研「2024 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 市場編」
クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」は、株式会社富士キメラ総研の「2024 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 市場編」において、「端末管理・セキュリティツール(ソフトウェア)」2023年度市場シェア1位(ベンダーシェア)を獲得しました。
今後もお客様により高いご満足を提供すべく、商品およびサービスのさらなる品質向上に取り組んでまいります。
利用者様の声
SKYSEA Client Viewは、大手企業様から中小規模の企業様まで幅広くご利用いただいております。
ここでは、社員数300名以下の企業様のお声をご紹介したいと思います。
リモートワーク中の仕事の見える化
業務の進捗が見えにくいことで心配だったリモートワーク。実際に運用してみると、心配していたとおり仕事が遅れ気味で残業が増えた事例も見受けられました。そこで、SKYSEA Client ViewでPCの操作ログを調べることに。利用したアプリケーションやそれを操作した時間、作成したドキュメントなどから、リモートワーク中の業務状況が把握でき、社員に適切な助言や指導ができるようになりました。
サービス業 社員数200名
業務時間の把握
リモートワークでも労働時間はオフィスにいるときと同じように管理しなければなりません。出勤や退勤はWeb上で行えるようにしていますが、実際にPCを使っている時間、使っていない時間などの実態は不明でした。SKYSEA Client Viewを導入したことで、リモートワーク中にPCで業務している時間を把握できるようになりました。
製造業 社員数150名
適切な情報の取り扱いを推進
リモートワークでは一人で作業することも多く、周りには私物のUSBメモリやハードディスク、プリンターなどが存在する可能性もあり、情報が持ち出されやすい環境になります。取引先にご安心いただくためにも、適切な情報管理が求められていました。SKYSEA Client Viewを導入したことで、リモートワーク中でもUSBメモリなどのデバイスの接続を禁止したり、どんなファイルを誰がいつ取り扱ったかを操作ログとして取得できるようになり、会社の重要な情報を適切に取り扱う体制を推進できました。
専門サービス業 社員数70名


