
昨今のビジネスシーンでは、業務においてクラウドサービスの活用がごく一般的なものとなっています。企業活動を行う上で、クラウドサービスを安定的に運用・活用していくためには、クラウド環境の稼働状況をチェックするクラウド監視が不可欠です。この記事では、クラウド監視の目的や方法、さらにはクラウド監視で必須となるツールの選択肢についてわかりやすく解説します。
クラウド監視とは、クラウド環境の稼働状況を監視すること
クラウド監視とは、クラウド環境の稼働状況を常時監視することです。自社の企業活動において使用しているクラウド環境のパフォーマンスを維持するためにも欠かせない取り組みといえます。まずは、クラウド監視が必要とされる理由や、主な監視対象について解説します。
クラウド監視が必要な理由
自社の事業において、SaaS(Software as a Service)などのクラウドサービス活用がごく一般的なものとなりつつある昨今、サービスが問題なく稼働しているかどうかをチェックするクラウド監視は欠かせない仕組みとなっています。クラウドサービスが突然停止したり、障害を起こしたりすることによって、自社サービスが正常に運用できなくなることのないよう、事業者は24時間体制で監視しなければなりません。安定したサービスの提供や信頼性を維持するためには、クラウド監視を適切に実施していくことが重要です。
クラウド監視の対象
クラウド監視の主な監視対象は、クラウド上のシステムやアプリケーションの稼働状況、不正アクセスの発生状況などが挙げられます。クラウド環境はクラウドサービス、インターネット、組織内ネットワークなど、複数の要素によって構築されているため、各要素を適切に監視していくことが大切です。クラウド監視においてはこれらの各要素に異常が発生していないか常時監視するとともに、何らかの障害が検知された際には迅速に対応し、被害を最小限に抑える必要があります。
クラウドとオンプレミスの違い
クラウドと、自社のリソースでサーバーを構築・運用するオンプレミスでは仕組みが根本的に異なることから、監視対象と監視方法にも大きな違いがあります。クラウドはオンプレミスとは異なり、自社内にハードウェア類を設置・保有する必要がありません。そのため、オンプレミスでは必須とされるハードウェア監視の必要がない点が大きな特徴です。クラウドサービスの場合、事業者が提供するサーバーのCPUやメモリ、ストレージなどのリソース使用量、ネットワークトラフィック、ログファイル、セキュリティなどに関するデータを監視することになります。
クラウド監視の目的
前述のとおり、クラウド監視ではさまざまな領域の監視を行いますが、クラウド監視を行う目的にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、クラウド監視の目的を大きく3つに分けて解説します。
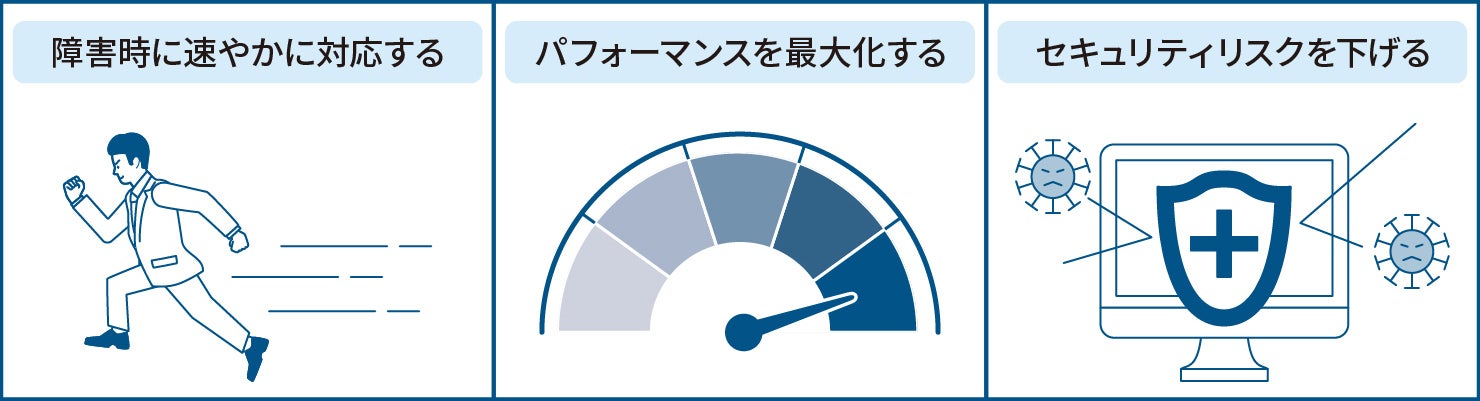
障害時に速やかに対応する
クラウド環境で発生した障害をいち早く検知し、速やかに対応するためにも、クラウド監視はとても重要です。クラウドサービスが提供するアプリケーションの動作が顕著に遅くなったり、ネットワークに異常が検知されたりするようなら、何らかのトラブルが発生していることが想定されます。そういったトラブルが深刻化する前に対処をしなければ、業務停止や顧客へのサービス提供の停滞につながりかねません。顧客や取引先の信頼を失う事態を避けるためにもクラウドは常時監視し、有事の際は速やかな対応が求められます。
パフォーマンスを最大化する
クラウド環境において、アプリケーションのパフォーマンスを最大化することも、クラウド監視の主要な目的といえます。クラウドサービス事業者が提供するCPUやメモリ使用率、ストレージなどの使用量を常時監視し、リソースの逼迫を回避することが求められます。高負荷がかかっている状況などは早期に検知し、サーバーダウンの予防やリソース配分の最適化を図らなければなりません。
セキュリティリスクを下げる
クラウド監視を常時継続することは、セキュリティリスクの低減という点においても有効です。クラウド環境の稼働状況に何らかの異常が認められる場合、マルウェアへの感染や不正アクセスによる被害の可能性があります。複数の端末から大量のデータを送りつけることにより、サーバーをダウンさせるDDoS攻撃などの手口はその典型例です。こうしたインシデントの発生を早期に察知して初動対応につなげることも、クラウド監視の大きな目的です。
クラウド監視の主な要素
クラウド監視の主な要素としては「死活監視」「サービス監視」「リソース監視」が挙げられます。ここでは、それら各要素にはどのような確認が必要なのか見ていきます。
死活監視
死活監視とは、クラウドサーバーやアプリケーションが稼働しているかどうかを確認することを指します。サーバーがダウンしていたり、アプリケーションが作動しない状況に陥っていたりするようなら、障害が発生していることは明白です。システム全体に重大な影響が及んでいなかったとしても、障害を放置すればトラブルや不具合が発生することは想像に難くありません。本来稼働しているべきソフトウェアやミドルウェア、ネットワークなどが停止していないかを常時チェックしておけば、障害も早期に検出できるため、深刻な事態へと発展する前に対策を講じることができます。
サービス監視
サービス監視とは、システム自体が稼働していたとしても何らかの異常が検知されていないか監視することを指します。例えば、ユーザーが意図していない動作が確認されたり、動作が顕著に遅くなっていたりするようなら、何らかの障害が発生している可能性があります。実際、サービス監視によって検知された異常がサイバー攻撃の早期発見につながるケースも少なくありません。システムが動いてさえいれば良いと捉えるのではなく、異常な動作が見られないかも常時監視していく必要があります。
リソース監視
リソース監視とは、クラウドサービス事業者から提供されるサーバーのCPUやメモリ、ストレージに高負荷がかかっていないかをチェックすることを指します。こうしたリソースに高い負荷がかかる状態が続くと、アプリケーションの動作が極端に遅くなったり、サーバーがダウンしたりする原因にもなりかねません。リソース監視を常時継続しておけば、平常時と比べて高い負荷がかかっているかどうかを判断できるため、サーバーダウンなどの前兆にも気づける可能性が高まります。
また、リソース監視を通じて得られたデータは、今後のリソース配分を検討する際にも役立ちます。システムに常時高い負荷がかかっているようならリソースの増設を検討しなくてはなりません。反対にリソースが余り過ぎているようなら、ダウンサイジングを検討したほうがいい場合もあります。クラウドサービスの多くは容量に応じて料金プランが設定されているため、費用対効果を最適化する上でもリソース監視は適切に実施していくことが大切です。
クラウド監視ツールの選択肢
クラウド監視の仕組みを構築する方法には、いくつかの選択肢があります。主なパターンとして挙げられるのは以下の4点です。
クラウドサーバー事業者の監視ツール
自社が利用しているシステムがクラウド環境で完結している場合には、クラウドサーバー事業者がクラウド環境と併せて提供している監視ツールを活用できます。これは、クラウド監視をシンプルかつ適切に行う上で有効な手段といえます。ただし、クラウドとオンプレミスを併用している場合には注意が必要です。クラウドサーバー事業者から提供される情報は、あくまでもクラウド関連のデータに過ぎません。自社が保有するシステムに関しては、クラウドとは別の監視方法を確立しておく必要があります。
SaaS型の監視ツール
クラウド監視に対応しているSaaS型の監視ツールを活用する方法もあります。クラウド監視に求められる基本機能が備わった既製品を活用すれば、導入の工数や監視ツールの開発にかかるコストを抑えられます。しかし、あくまでも提供されている機能の範囲内でクラウド監視を進めることになるため、あらゆるニーズに応えられるとは限りません。自社にとって必須の監視項目を利用できないようなら、後述する自社開発やアウトソースといった別の手段を検討する必要があります。
自社で監視ツールを構築する
自社で独自に監視ツールを構築し、導入・運用していく方法もあります。自社で監視ツールを構築する場合、既存のSaaS型監視ツールなどを導入する場合と比べて構築にかかる工数や期間、コストがかさみやすい一方で、自社の用途に応じて柔軟にカスタマイズできるという大きなメリットがあります。自社独自のツールを構築・運用する技術力が備わっており、費用面や導入までの期間に余裕がある場合にお勧めの方法です。
監視の専門業者にアウトソースする
クラウド監視をアウトソースする方法もあります。クラウド監視に必要な環境構築から運用までを一貫して実施してもらえるサービスを活用するのも一つの選択肢です。アウトソースによってクラウド監視を行うと、スムーズな導入と運用開始が期待できることに加え、自社のリソースを必要最小限に抑えられるため、コア業務に集中しやすくなるメリットがあります。クラウド監視に必要なシステム構築や運用に関するノウハウが備わっていない場合など、クラウド監視のためのリソースを割く余裕がない場合にお勧めの選択肢です。
クラウドサービスを導入している企業にとってクラウド監視は不可欠
クラウドサービスをビジネスで利用している企業にとって、クラウド監視は欠かせない取り組みといえます。リソースの逼迫や障害の発生により、システムが正常に動作しなくなったり停止したりするようなことがあれば、企業の信頼に関わる重大な事態にも発展しかねません。安定的に事業を継続していく上で、クラウド監視は重要な経営課題の一つとなり得ます。
クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」は、日々蓄積されるデータを活用し、IT資産運用の傾向を適切に把握するためのさまざまな機能を搭載しています。「Webアクセス解析」では、クラウドサービスなどへのアクセス状況をレポートとして集計したり、時間別にアクセス数をグラフ化したりすることが可能です。IT資産運用の傾向を具体的に把握しながら、変化を察知するツールとしても活用できます。
IT資産運用の傾向を適切に把握したい事業者様は、ぜひ「SKYSEA Client View」の活用をご検討ください。
お問い合わせ・カタログダウンロード
「SKYSEA Client View」のお問い合わせ・資料ダウンロードはこちらから